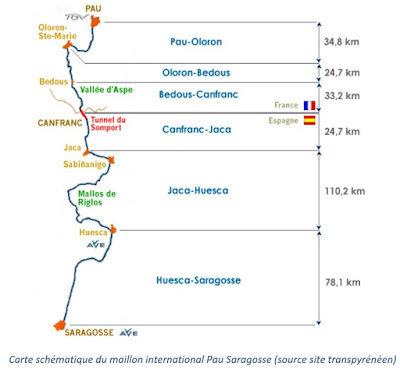- 情熱の大輪ループ線
ピレネー山脈よりも南のイベリア半島はいわゆるヨーロッパとは気候も雰囲気も大きく異なります。歴史上イスラム教の影響下にもあったこともあります。
 |
| 1910年ごろのスペインの鉄道路線図 ループ線は図中央のレオンから海沿いのアコルーニャに向かうオレンジ色の線上にあります 図中の黒い線はメーターゲージの路線です。 |
さて、一時期は世界征服も夢ではなかったスペイン帝国ですが、17世紀に入るとイギリスに海上での争いで負けて没落してしまいきます。18世紀には王朝が途絶えたり、ナポレオンのフランスに占領されたり、アメリカと戦争してぼこぼこにされたり、まさに踏んだり蹴ったりの100年間を経験します。
鉄道もヨーロッパ諸国が1848年にバルセロナで開通したのが最初で、他のヨーロッパ諸国と比べると10年~20年程度遅れていました。
それでも1850年代には鉄道投資熱の高まりに乗って各地に鉄道が建設されており、急速に路線網拡大していっています。
そんな中でどうしても海岸沿いに出るところで急勾配になる地形的制約に苦しめられることになります。イベリアゲージと言われる1668mmのブロードゲージは山間部の路線建設にひどく難航し、標準軌を採用しなかったことを当時のスペインの鉄道技術者は随分後悔したそうです。スペインでは海岸沿いを中心に1000mmのナローゲージ路線が残っているのは山間部のブロードゲージ路線建設を諦めてナローゲージ路線を敷設した名残です。
このア・コルーニャ線も内陸側からはブラニュエラスまでが1868年に、海岸側からはルーゴまでが1875年に開通していましたが、ループ線を含む部分の開通は1883年のことになります。この間、列車はブラニュエラス止まりで「coachでルーゴまでの約50kmを連絡していた」そうです。ここでいうcoachはバスではなく文字通り馬車だろうと思います。ヨーロッパではゴッタルドバーンに次ぐトップクラスの歴史の古いループ線でもあります。
もともと海洋国家だったスペインは海岸沿いに有力都市が多くあり、王室のあったマドリードと海岸沿いを結ぶ路線はどこも重要路線だったと言えます。ア・コルーニャ線もそのような海岸沿いの有力都市と首都を結ぶ幹線と位置付けられています。
- いまだ色あせない往年の世界一
輪の大きさは一周5.8kmあり、1883年の開通から2004年に中国の水柏線の3重ループ線が開通するまで実に120年間、世界最大のタイトルを保持していました。曲線半径は最小280m、勾配は20‰、輪の大きさを目一杯使ってトータル220mの高低差を登ります。建設時期を考えるとかなりの高規格と言えるでしょう。

 |
| あまりにも輪が大きいのでループ線ぽい写真は撮りづらいようです ループ線の向き(写真では右巻き)とは逆の左カーブである点も注目 |
この「ループ線の途中に、ループとは逆向きの曲線のあるループ線」というのはあまり他に思い当たりません。世界唯一とは断言しにくいのですが、かなり珍しいものだと思います。
レオン側から来ると台地の上のブラニュエラス駅を出て山の尾根沿いに進み、5km以上もあるループ区間を通り、トンネル・デル・ラソで自線の下をくぐります。ラソはスペイン語で輪の意味なので、英語に訳すとループトンネルというそのままの名前になります。
また、現在の世界の大輪ループ線を見てみると、1位の韓国のソラントンネルは全区間トンネル内、2位の中国水拍線も全体の3分の2がトンネル内ですが、このグランハ・スパイラルは交差部のトンネル・デル・ラソも含めて比較的短いトンネルばかりです。大きな谷を豪快に見下ろす長いループ線の車窓風景は抜群です。(ちなみに4位はブルガリアのシプカ峠のループ線、ここもあまり車窓には期待できません)
- 将来不透明ながら、今のところは特急街道
 | |
| ラグランハ駅を通過する特急列車 こちらからお借りしました |
ここは現在でも西部ガリシア州と首都マドリードを結ぶ幹線となっており、毎日3往復~5往復の特急列車、2往復のローカル列車、2往復の夜行特急が走っています。
もともと幹線規格の線路をかなり高速で列車が行きかう様子はなかなか迫力があります。一応160km対応らしいですが、動画で見る限りそこまでスピード出ていません。
また、他のヨーロッパ諸国のローカル線同様、ここもローカル列車が思い切り減便されています。
実は現在マドリードからポルトガルとの国境沿いを通って沿岸部を結ぶ標準軌の高速鉄道線が建設中で、そちらが開通すると一気に立場が危うくなる可能性があるので要注意な区間ではあります。
次回は中国のループ線をご紹介します。